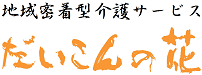小規模多機能型居宅介護とは
①小規模多機能型居宅介護ってなんですか??
小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者様、御家族様の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。
また、必要であれば一時的な長期宿泊も可能です。
法制度化される平成18年4月以前、小規模多機能型居宅介護は、「宅老所」という名称で存在していました。
「宅老所」は、大規模老人施設とは違い、介護や支援を必要としている高齢者に既存の民家等でサービスを提供することにより、気の知れた仲間同士と家庭的な雰囲気で過ごすことができるというものでした。
大規模老人施設の整備が進む中、一方では、理想的な介護の在り方である、「宅老所」でのケア実践を行う事業所が増えていったのです。
介護や支援が必要な高齢者にとって、気を遣わず、信頼関係が構築しやすい、小規模の「宅老所」は理想的な形態でした。
特に、要介護者の半数を占めるといわれる認知症高齢者にとっては、住み慣れた地域で、できるかぎり環境を変えずにケアを受けることができるということが大切なのです。
「宅老所」が実践してきた、住み慣れた地域と小規模ならではの家庭的な雰囲気にこだわったケアは、高齢化が急速に進む日本において認められ、法制度化する運びとなったのです。
昔は、家族や隣近所で支えあってきた高齢者のケアも、現在では、核家族化が進み、近所付き合いも少なくなっています。そんな、昔の良き時代を再現すべく、地域ケア・コミュニティーの拠点として小規模多機能居宅介護は注目されています。
24時間365日体制で、切れ目無く介護サービス(通所・宿泊・訪問)を提供できる小規模多機能型居宅介護は、在宅生活を送る要介護者の強い味方になっています。
小規模多機能型居宅介護は、便利で安心感のある、言わば介護のコンビニエンスストアなのです。
②どんな人が利用できますか?
施設と同じ市町村に住民票がある人、65歳以上の要介護者(要支援1~要介護)が入居できます。(他市町村でも市同市での協議の結果、利用できる場合もあります。)
看護師が常置しておりますが、医療依存度によって利用が叶わない場合もあります
③サービスの特徴は?
①小規模多機能型居宅介護ってなんですか?でも説明させて頂いておりますが、利用料金の面では介護保険個人負担分(1割~2割)が定額となるため、たくさん利用しても一定額を超えることがありません3つのサービスを1つの事業所の職員で提供するため、施設でも自宅でも同じ顔ぶれの職員が対応します。
急な利用、時間変更が容易にできます
③間取り
施設全体の間取りは下記をクリックしてください●肥田瀬(グループホーム)平面図
●肥田瀬(小規模多機能型居宅介護)平面図
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
・3つのサービスを臨機応変に利用できる ・認知症専門のスタッフも常駐している ・アットホームな雰囲気 ・1カ月あたりの利用料が定額なので、毎月の介護費用が膨らみすぎない。 ・金銭面で心配な方には利用料から逆算して利用プランを組むことができる ・食事のすべてが手作りのため美味しい ・スタッフが活き活きとしている ・基本生活は本人の意向や希望で決まる ・生活全般をスタッフが行わず、介助を通じて一緒に楽しみながら行う ・送迎の時間、食事の有無などの変更も容易に可能 ・顔なじみのスタッフや利用者との交流がはかりやすい ・共用空間が広く明るい |
・施設と同じ地域に住民票がないと利用できない(全国共通・例外あり) ・共同生活に合わない方には逆にストレスになることもある ・重度化した場合に対応できない場合がある(医療連携で生活できる場合は可能) ・他の介護保険サービスの中には併用できないサービスがある ・現在受けているサービスから小規模多機能へ移行する際、ケアマネージャーが変更となる |